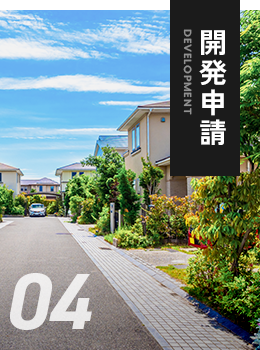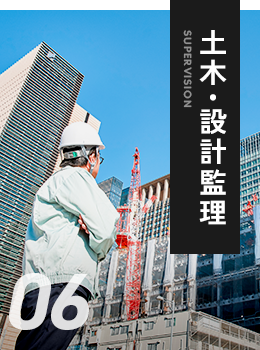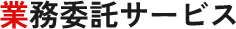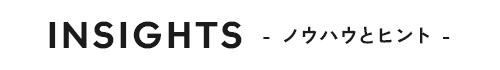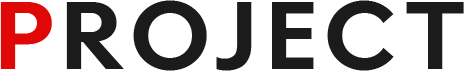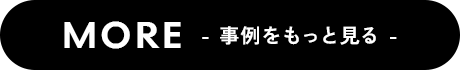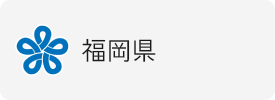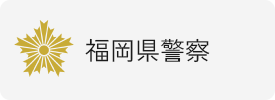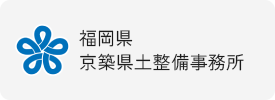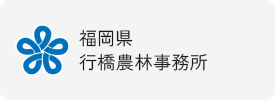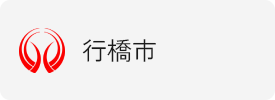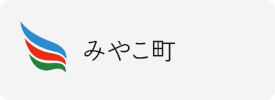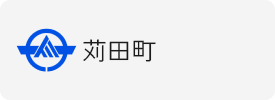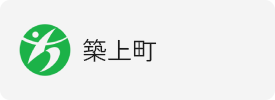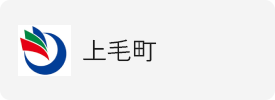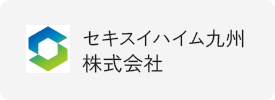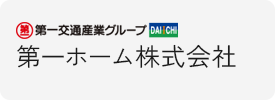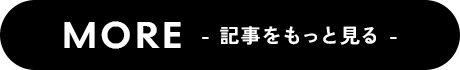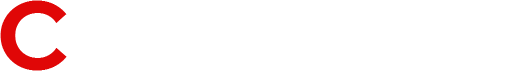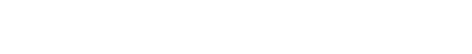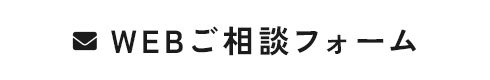「コスト」と「クオリティ」をチェックするパートナー
それがM.B.iの「コンストラクション・マネージメント」です
建築プロジェクトで、本当に頼りになるパートナーはいますか?
私たちの役割は、建築プロジェクトにおいて、企画設計から品質管理、コスト管理、スケジュール管理まで
発注者であるあなたに代わってすべてに目を光らせる「コンストラクション・マネージメント」です。
建築コストの変動や欠陥による損害に立ち向かうのが私たちの仕事。建築プロジェクトにおけるリスクからあなたを守ります。
一般の方が建物を築く機会は限られており、大規模開発では失敗は許されません。
私たちはその不安を解消し笑顔が絶えないよう、地方自治体や大手住宅メーカーより業務委託を受け培った知恵を駆使してお手伝いします。
-
あなたに代わり資材価格を徹底比較し
独自ルートで仕入れまで行います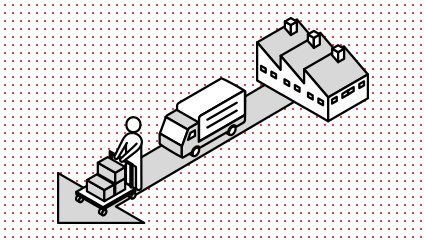
建築プロジェクトにおいて、通常は総建築費の40%〜50%が資材設備費に充てられます。そこで当社は資材・機材・製品等の入手ルートを徹底的に調査し品質を落とさず仕入れ先の変更により費用削減を実施。総建築費より10〜15%のコストカットを実現しています。
-
測量&土木造成設計により
手頃価格の土地を最大限に活用します
多くの場合土地取得から建築は始まります。この土地取得費用圧縮も私たちの仕事です。高価な土地を買うより、安価な土地を土木技術により造成した方がメリットが高いケースも。自治体から業務委託される確かな造成設計でコスト削減に貢献します。
-
デザインと使い勝手を重視しつつ
低コストを実現する建築設計を行います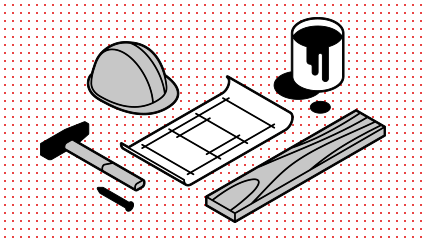
多くの設計事務所はデザイン性のみ追い求めコスト意識が低いのが実情です。しかしコスト削減に最も貢献できるのが設計の段階、お客様のニーズを叶えつつ如何にコストパフォーマンス良く建てるか、この難題に応える設計士がお手伝いします。
-
欠陥を作らないノウハウで
安心を創ります
当社は欠陥住宅の調査・原因研究を長年行っております。欠陥の多くは施工スタッフの技術不足で、正しい知識を持った者がフォローすれば防げるケースが殆どです。私たちが公正・公平な立場で建築現場で目を光らせ、問題発生の前に施工指導を行います。
「成功するプレゼンテーション」
M.B.iの知識と経験を総動員し、お手伝いします
エビデンスに基づく提案は、クライアントの心を魅了します。
単に 「デザイン性」 だけではなく、「機能性」 と「経済性」の絶妙なバランスが、成功を手にする鍵です。
クライアント様のニーズを見極め、競合他社に優るコスト効率の高いプランを、私たちは実現できます。
私たちは、御社の一員として、または外部コンサルタントとして、あなたが望む形でプレゼンテーションを成功へと導きます。



コンストラクション・マネージメントは
プロジェクトの大小関わらず依頼頂けます
自治体向け、民間向け、それぞれのニーズに合わせた提案が可能です
九州福岡を中心に、全国規模でご要望をお伺いします
ご利用団体・企業の一例 (順不同)
-
2023.12.31 資金計画の重要性
-
2023.12.31 予算に合わせた家づくり
-
2023.12.31 魅力的なデザイン
-
2023.12.31 二人三脚でお客様の想いをカタチに